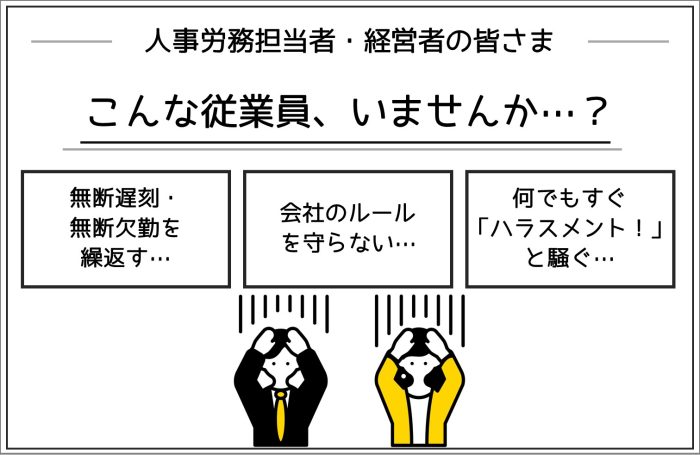「アルバイトにのみ説明すべきこと」があるのか?
Q:アルバイトの従業員より
- 2021年4月から中小企業に対しても同一労働・同一賃金に対応しなければならない。
- パート労働者に同一労働・同一賃金実態を説明する義務があると聞いている。
- 契約書の労働条件通知書に実態に関する記載がなかったが、新規に通知書を書き直して交付するべきではないか?
という質問を受けました。法令違反になっているのでしょうか?会社として、アルバイト従業員やパート従業員に対して、どこまで説明責任をはたさなければならないのでしょうか?
より丁寧に説明するのは、当然ですが、法令違反か否かのボーダーラインはどこにあるか確認させてください。
アルバイト・パートのみ説明が必要な事項がある
A:アルバイトやパート従業員といった、短時間労働者の方とのコミュニケーションという点に的を絞って解説します。
質問をしてきたアルバイトさんへの回答について
今回質問を挙げてきた、アルバイトの従業員に対しては、
- 労働条件通知書には、昇給などの記載は必須であるが、均等待遇の実態まで記載する義務はない。
- 待遇の違いについては、「質問があった場合は説明する」が法的な義務であり、積極的に伝達することまで求められていない。
- そのため、待遇の違いについては、雇用契約書や就業規則に特別に記載することは行っていない。
- 必要であれば説明するので、具体的にどのようなことを確認されたいのか教えて欲しい。
と回答するのがボーダーラインの回答になります。
アルバイト・パート従業員には、何を説明しなければならいのか?
通常のフルタイムの従業員と異なり、アルバイトやパート従業員のような短時間労働者の方に、追加で対応しなければならない点は以下の5点になります。
- 雇入れの際/契約更新の際に、労働条件を文書で明示する(第6条)
- 雇入れの際/契約更新の際に、雇⽤管理の改善措置の内容を説明する (第14 条 第1項)
- 求めがあった際は、通常の労働者との待遇の相違の内容・理由や待遇の決定に当たって考慮した事項を説明する(第14 条 第2項)
- 相談に対応するための体制を整える(第16 条)
- パートタイム・有期雇用労働者から苦情の申出を受けたときは、自主的に解決するよう努める(第22条)
(1)「雇入れの際/契約更新の際に、労働条件を文書で明示する」について
フルタイムの従業員であっても、労働条件の通知は文書で行わなければなりませんが、アルバイトやパート従業員に対しては、通常に通知しなければならないことに加え、「昇給の有無」「退職手当の有無」「賞与の有無」「相談窓口」の4点も記載することが必要になります。
これは、雇入れだけではなく、労働契約の更新時も含みます。
契約更新時も労働条件通知書は渡していなければ、健全な状態ではありませんので、新規雇用のときの書式を使えば、負担なく対応できるでしょう。
ちなみに、ここでの「昇給」とは、一つの契約期間の中での賃金の増額のことを指し、契約更新時の賃金改定があり、期間中は定期昇給は無いのであれば「昇給はなし」となります。
(2)「雇入れの際/契約更新の際に、雇⽤管理の改善措置の内容を説明する」について
パートタイム・有期雇用労働者を雇い入れたとき(労働契約の更新時を含む)は、事業主は、実施する雇用管理の改善に関する措置の内容を説明することが義務付けられています。
- 賃金制度はどのようなものとなっているか
- どのような教育訓練があるか
- どの福利厚生施設が利用できるか
- 正社員への転換推進措置としてどのようなものがあるかなど
を説明していきましょう。個別に説明する方法でも構いませんが、、雇入れ時の説明会等に、複数のパートタイム・有期雇用労働者に同時に説明を行うことも差し支えないとされています。
(3)「通常の労働者との待遇の相違の内容・理由や待遇の決定に当たって考慮した事項を説明する」について
パートタイム・有期雇用労働者から求められたとき、事業主はそのパートタイム・有期雇用労働者と通常の労働者との間の待遇の相違の内容及び理由と、待遇を決定するに当たって考慮した事項を説明することが義務付けられています。
- 比較対象の通常の労働者との間で待遇の決定基準に違いがあるか、違う場合はどのように違うのか・なぜ違うのか
- 教育訓練の実施や福利厚生施設の利用の決定に当たり何を考慮したか(通常の労働者との違いがある場合は、なぜ違うのか)
- 正社員への転換推進措置として講じる措置の決定に当たり何を考慮したか
ということを説明していきましょう。
「パートタイム・有期雇用労働者から求められたとき」に説明しなければなりませんので、求めが無い時に説明しなかったとしても違法にはなりません。
(4)「相談に対応するための体制を整える」について
パートタイム・有期雇用労働者からの相談に応じ、適切に対応するための必要な体制(苦情を含めた相談に応じる窓口等の体制)を整備することが義務付けられています。
「相談窓口」とは、パートタイム・有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口になります。一般的には総務部・人事部となるでしょう。なお、窓口は「総務部○○」など個人でも構いませんし、「総務部相談窓口」というように組織でも構いません。
(5)「パートタイム・有期雇用労働者から苦情の申出を受けたとき」について
当たり前になりますが、トラブルが発生したら社内で解決しましょうということになります。
「努める」と努力義務となっているので、「頑張ってやってみたが、できなかった」となっても、お咎めはありません。
あわせて読みたい