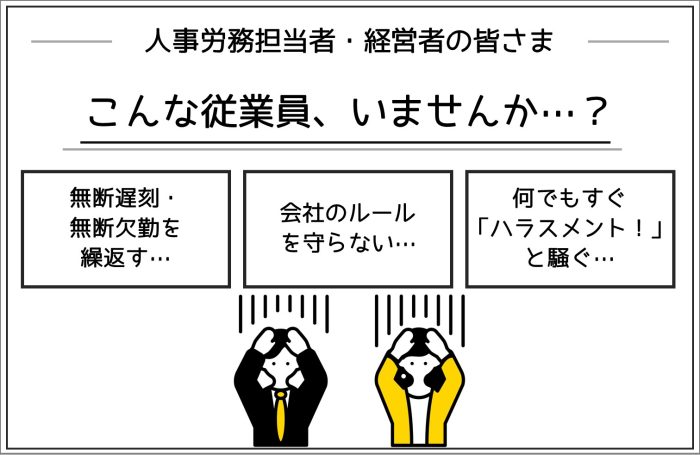【質問】実費精算制度を新入社員にのみ適用できるか
当社ではこれまで、通勤費を公共交通機関を基準に定額で支給していましたが、実際には自家用車や自転車で通勤する社員も多く、実態に合わない支給方法に課題を感じています。
特に今後入社する社員に対しては、実費精算制度(例:ガソリン代)を導入したいと考えています。既存社員については、現状の支給を継続する予定ですが、新制度導入の進め方や注意点について教えていただけますか?
【回答】制度設計と就業規則の整備で導入可能
出勤手段ごとに支給ルールを整理する
まずは、社員がどのような手段で通勤しているか(車、電車、自転車など)を把握し、支給対象を明確にする必要があります。 たとえば、
- 電車通勤:従来通りの定期代
- 自動車・バイク:自宅から会社までの距離が一定以上(例:2km)であれば支給
- 自転車:通勤距離や駐輪場代の支給条件を設定

通勤実態の把握と分類が導入の第一歩です。
実費精算の計算方法を決める
ガソリン代の精算は、次のような方法が一般的です:
- 通勤距離(往復) × ガソリン単価(会社が指定) × 年間出勤日数 / 12
ガソリン単価は四半期ごとに見直し、通勤距離は本人申請とします。単価や計算式は就業規則に明記することでトラブルを回避できます。

頻繁な見直しが難しい場合は、変更できる権限だけ設けておくと柔軟です。
その他の通勤条件も整理しておく
自動車通勤を認める場合は、駐車場の指定や任意保険加入の確認などもセットで運用するのが安全です。

交通費支給と合わせてリスク管理の整備も重要です。
就業規則・雇用契約書の修正が必要
新制度を導入するには、就業規則や雇用契約書の中で「支給条件」「申請義務」等を明記する必要があります。 通勤手段の変更があった場合の申請義務も記載しておきましょう。

就業規則の明文化が後々のトラブル予防になります。
入社時に申請書を提出してもらう
新たに入社する社員には、「通勤経路申請書」を提出してもらい、使用手段や距離を記入してもらう様式に変更しましょう。

初期運用の徹底がその後の制度定着に影響します。
既存社員に制度を適用しない方法
既存社員の交通費は従来通りとし、新制度は新入社員のみに適用することは可能です。
就業規則に「●年●月●日以降の入社者に適用する」と明記すれば問題ありません。

出戻り社員や再雇用社員の扱いは個別に検討しましょう。
新制度の導入には、通勤手段の整理、支給基準の設定、そして就業規則や契約書の整備が不可欠です。
実費精算制度は通勤実態に即した制度として、今後の通勤環境の多様化に対応する手段となります。
既存社員との不公平感を防ぐためにも、対象者の明確化と制度説明の丁寧さが重要です。

この記事は、頻出のご相談事例をもとに生成AIで作成しました。
生成AIでは「それらしい」回答は作れますが、”正確”や”現実的”という面で、経営と人事の世界で回答を利用するには物足りなさが残ります。
お客様の経営状況や人間関係を踏まえた上で、伝え方も含め、現実的な着地点をご提案することは、私たちが得意とする領域です。
記事をご覧になり、「弊社ならどうすれば良い?」と感じられた経営者様・人事担当者様は、ぜひ、私たちにご相談ください。