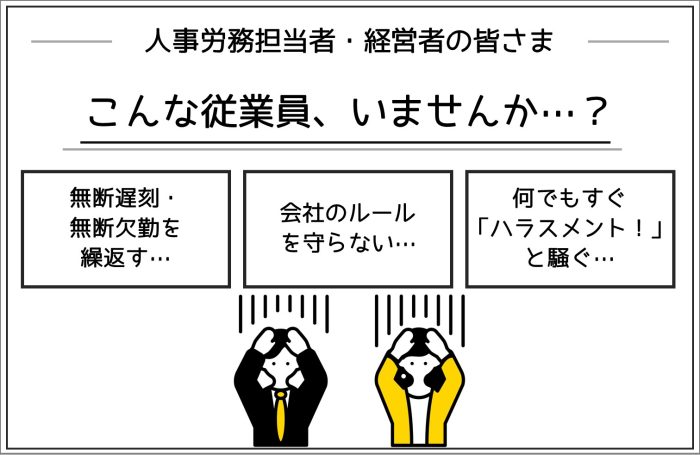年末年始に勤務した従業員へ支給する手当について、「賞与」として取り扱うべきか、通常の給与として扱うべきか――社会保険の観点からも慎重な判断が求められるテーマです。今回は、実際に年金事務所から指摘を受けたというケースをもとに、考え方と対応策を整理します。
【質問】年末年始手当は賞与として届け出る必要があるのか?
年末年始勤務に支給する手当について、年金事務所から「賞与扱い(賞与支払届の提出)」とするよう指導を受けました。どのように対応すべきでしょうか?
【回答】支給実態が定期的・勤務対価であれば、賞与ではなく給与として扱うのが原則
定期的・固定的に支給される年末年始手当は、原則「給与」として取り扱われます。
ご質問のケースでは、年末年始手当があらかじめ支給規程で定められており、勤務日数や勤務時間に応じて定額を支給しているとのことです。このような手当は、たとえ名称が「慰労金」であっても、実態としては労働の対価として定期的に支給される給与の一部と評価されるのが一般的です。
年金事務所から賞与として処理するよう指導を受けたとのことですが、対応にあたっては以下のような確認と対応が重要です。
担当者名と指摘の根拠を確認する
まずは年金事務所の担当者氏名と、指摘内容の法的根拠を明確にしましょう。
年金事務所の見解は職員によって差があることもあり、対応内容を記録に残すことが後のトラブル防止になります。また、指摘の根拠があいまいであれば、他の事業所や業種との整合性にも着目すべきです。

行政機関の指導は拘束力を持つものではないため、納得がいかない指摘に対しては事実関係と解釈の整理を行ったうえで、異議を唱えることも可能です。
実態が「定例支給」なら賞与ではない
年末年始勤務の対価であり、定期的に支給されているなら、賞与として処理する必要はありません。
たとえば運輸業や工場などでは、年末年始勤務に対して「年末運行手当」や「年始勤務手当」などの名称で毎年同様の支給が行われていますが、これを賞与として届け出るケースは極めて稀です。名称に「慰労金」とあっても、それが労働の対価であり、定期性・継続性がある場合は通常の給与として処理すべきものです。

賞与と評価されるか否かは、支給の「実態」に基づく判断が原則です。名称や支給月だけで判断しないよう注意が必要です。
賞与として届け出るリスクと対応策
賞与として処理する場合、報酬月額や社会保険料の計算に影響が出ることがあります。
賞与支払届を提出することになれば、賞与に対する保険料が別途発生します。また、手当額や支給タイミングによっては、標準賞与額の上限超過や不均衡な負担を生む恐れもあります。
指摘を受け入れるかどうかの判断にあたっては、他社の事例や業界での運用慣行を確認し、社内で判断基準を明文化しておくとよいでしょう。

社会保険の手続きが煩雑になるため、不用意に賞与処理へ移行することは避けた方がよいケースが多いです。行政側の判断が不透明な場合は、社会保険労務士など専門家の意見を踏まえて対応を決めることをおすすめします。
名称より「支給の実態」に注目を
年末年始手当の取り扱いにおいては、名称よりも実態が重要です。あらかじめ規程に定め、勤務時間や日数に応じて支給しているのであれば、それは「給与」であり、賞与とは別物と評価されます。仮に行政機関からの指摘があったとしても、根拠を明確に求め、事実に基づいて冷静に対応することが大切です。
このようなケースにおいては、規程の見直しや他社事例の収集といった予防的な対応も含め、専門家の意見を活用しながら、組織としての方針を固めておくことをおすすめします。

この記事は、頻出のご相談事例をもとに生成AIで作成しました。
生成AIでは「それらしい」回答は作れますが、”正確”や”現実的”という面で、経営と人事の世界で回答を利用するには物足りなさが残ります。
お客様の経営状況や人間関係を踏まえた上で、伝え方も含め、現実的な着地点をご提案することは、私たちが得意とする領域です。
記事をご覧になり、「弊社ならどうすれば良い?」と感じられた経営者様・人事担当者様は、ぜひ、私たちにご相談ください。