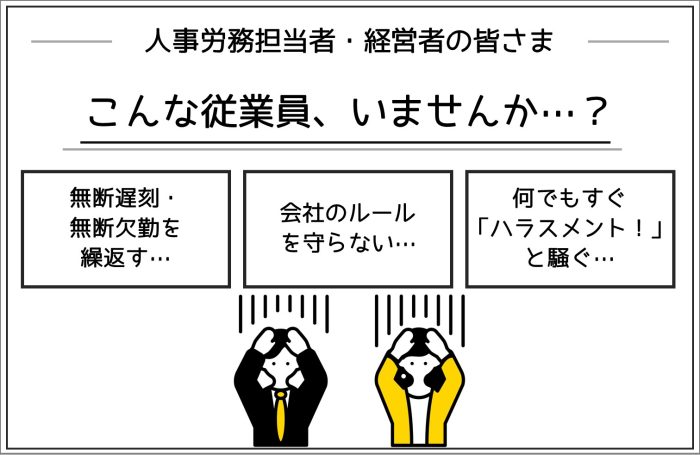【質問】副業規定の見直しと申告制への移行
就業規則では副業を禁止していますが、実際には黙認状態です。他社の運用事例を参考に、副業を申告制にしたいと考えています。どのような制度設計が適切でしょうか?
弊社では就業規則に「許可なく他の業務に従事したとき」を懲戒の対象としています(社員・パート共通適用)。しかし実際には、社員は1日8時間、週40時間働いており副業をしていないものの、パートについては副業を黙認しているのが現状です。
また、規則上は禁止としているため、パート募集時に「WワークOK」とは記載しづらく、採用にも支障が出ています。こうした背景から、現在のグレーな運用を改め、申告制に切り替えることを検討中です。
顧問先や他社における副業の申告制運用について、参考になる事例があれば教えてください。
【回答】副業の可否を明文化し、実態に合った制度設計を
副業に関する規定を現実に即した内容に見直し、申告制とすることで運用上のトラブルを防げます。
上場企業と中小企業では副業対応が異なる
上場企業は申告制が主流、中小企業は厳格または放任型が多い。
上場企業では、原則として終業後の副業は認めつつも、競業や信用毀損行為があれば懲戒処分としています。厚労省のガイドラインでも副業は届出制が基本で、労働時間の通算管理を目的としています。
一方、中小企業では副業を厳しく制限するか、全く管理しないケースが多く、厳格に管理する企業では誓約書を提出させたうえで届出制とし、違反時は懲戒処分としています。

ガイドラインを活用しながら、自社の規模や文化に合った柔軟な制度設計が求められます。
「禁止」ではなく、影響が出た場合に限定する表現に
副業そのものを問題視せず、結果に応じて対応する。
現行の「許可なく副業をした場合」という表現から、以下のような行為に該当した場合に懲戒対象とする文言に見直すことが現実的です。
- 労務提供上の支障が出た場合
- 企業秘密が漏洩した場合
- 会社の信用・名誉を損なう行為があった場合
- 競業により会社の利益を害した場合
このように、具体的な影響に焦点を当てる形にすることで、副業の是非ではなく業務への影響を基準とした運用が可能になります。

副業の一律禁止ではなく、問題が発生した場合に対応するスタンスのほうが、現代の働き方に適しています。
明文化と周知が制度定着の鍵
副業申告制を導入するには、社内ルールの整備と徹底した説明が必要です。
申告制とする場合は、届出書の提出や誓約書による責任明確化を行い、従業員に制度の趣旨を説明したうえで運用を始めることが大切です。また、申告内容については機密保持や業務への支障を確認し、会社側が許可・不許可の判断を行う仕組みにする必要があります。

制度だけ整えても、説明と運用が不十分であればトラブルに繋がります。導入時の説明会やQ&A整備も検討しましょう。
副業を申告制に移行する際には、就業規則と実態のズレを正すことが第一歩です。副業の一律禁止ではなく、業務影響を基準に対応する文言への見直しが現実的です。ガイドラインや他社事例を参考にしつつ、自社に合った制度を整備し、明確な運用ルールと周知徹底により副業を適切に管理していきましょう。

この記事は、頻出のご相談事例をもとに生成AIで作成しました。
生成AIでは「それらしい」回答は作れますが、”正確”や”現実的”という面で、経営と人事の世界で回答を利用するには物足りなさが残ります。
お客様の経営状況や人間関係を踏まえた上で、伝え方も含め、現実的な着地点をご提案することは、私たちが得意とする領域です。
記事をご覧になり、「弊社ならどうすれば良い?」と感じられた経営者様・人事担当者様は、ぜひ、私たちにご相談ください。