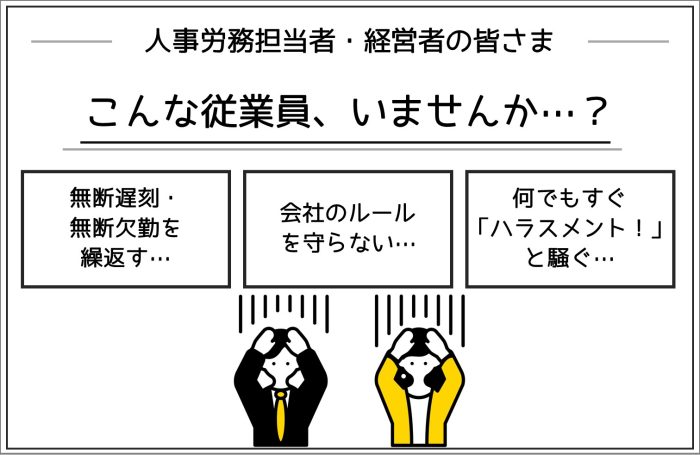【質問】懲戒処分後の自宅待機期間の給与支払いと留意点は?
懲戒処分が決まった社員を退職させる際、自宅待機期間の賃金支払いはどうすべきか?
セクシャルハラスメントの行為により、7月末付で合意退職することとなった社員についてご相談です。
懲戒処分が決まったのは7月中旬で、本人に7月末退職を申し渡しましたが、処分の厳しさと急な日程から、本人は「生活の都合があるので、できるだけ長く勤務を続けたい」と希望していました。
もともと本人から8月末退職の申し出があったこと、事件の重大性や引継ぎが完了している点などを踏まえ、会社として7月末での退職を要請。結果として本人も了承し、退職合意が成立しています。
ただし、7月10日以降は他の社員への配慮から自宅待機を命じており、就業規則では「処分決定までの自宅待機期間中は平均賃金の60%を支給」と定めています。
このような場合、懲戒処分決定から退職日までの期間も60%支給でよいのか、それとも100%支給すべきか悩んでおります。どう考えればよいでしょうか。
【回答】合意退職後の自宅待機期間は、原則60%支給で対応可能
自宅待機中の賃金は「会社都合の休業」として60%支給が妥当
ご質問の件、結論としては懲戒処分確定から退職日までの自宅待機期間については、平均賃金の60%を支給することで問題ないと考えられます。
雇用契約が続く限り、賃金支払いの義務はある
たとえ懲戒処分が下された後であっても、雇用契約は退職日までは有効に存続しています。そのため、労働者には労務提供義務があり、会社側にも賃金支払義務が残ります。
ただし、今回のように自宅待機を命じたのは会社側の都合ですので、休業補償として平均賃金の60%を支払う義務が発生します。
100%支給が必要とされるケースと規定の整備
法律上の「危険負担の原則」(民法第536条第2項)によると、会社側の都合で労務提供ができない場合は賃金全額の支払い義務があるとも解されます。
したがって、会社が就業規則等で「このようなケースでも60%を支払う」と明示しておくことが重要です。今回の就業規則が「懲戒処分が確定するまで」と明記されている場合、処分決定後は60%での支払い根拠が弱まる可能性もあります。
とはいえ、今回のように期間も短く、本人とも合意退職が成立しているケースでは、60%支給で実務的なリスクは小さいと考えられます。
処分に関連するリスクと今後の対策
以下、今回の事案に関連して注意すべき点をいくつか挙げておきます。
一事不再理に関する注意点
過去に当該社員の上司が始末書を回収して処分を済ませていた場合、その時点で何らかの処分があったとみなされ、「一事不再理」(同じ事案で二重に処分できない)に該当する可能性があります。
ただし、「始末書」を「顛末書」や「事実確認書」と位置づけることで、懲戒処分との重複を避ける配慮が必要です。
合意退職という建て付けの明確化
本人と合意のうえで退職届を受け取っているので、今回の対応は「合意退職」であり「諭旨解雇」ではないという整理が必要です。用語や文書上の表現にも注意を払いましょう。
再発防止の対応
処分と同時に、再発防止策の徹底と現場への周知も重要です。
- 管理職に対する「懲戒処分の手続きルール」の教育
- セクシャルハラスメントの再発防止指針の周知
- 被害者や周囲への配慮あるフォロー
も行うことで、職場環境の信頼回復につながります。

処分の妥当性だけでなく、その後の対応や文書の整理、組織への説明もトラブル予防の重要なポイントです。万一訴訟や社内混乱が起きた場合、「会社としてどのように対応したか」が問われることになります。感情的な対応ではなく、規程と法的視点に基づく行動が肝要です。
会社としての毅然とした対応と、慎重な言動・書面の整理を
今回のようなケースでは、本人との合意や規程の記載内容、文書の文言など、細かい点が法的リスクを左右します。感情に流されず、あくまでも就業規則や労働契約、民法上の原則に沿って対応しましょう。
処分は完了していても、組織への影響は継続します。再発防止策や管理職への教育を徹底することで、今後同じような問題が発生しないよう、企業としての信頼を高めていく必要があります。

この記事は、頻出のご相談事例をもとに生成AIで作成しました。
生成AIでは「それらしい」回答は作れますが、”正確”や”現実的”という面で、経営と人事の世界で回答を利用するには物足りなさが残ります。
お客様の経営状況や人間関係を踏まえた上で、伝え方も含め、現実的な着地点をご提案することは、私たちが得意とする領域です。
記事をご覧になり、「弊社ならどうすれば良い?」と感じられた経営者様・人事担当者様は、ぜひ、私たちにご相談ください。