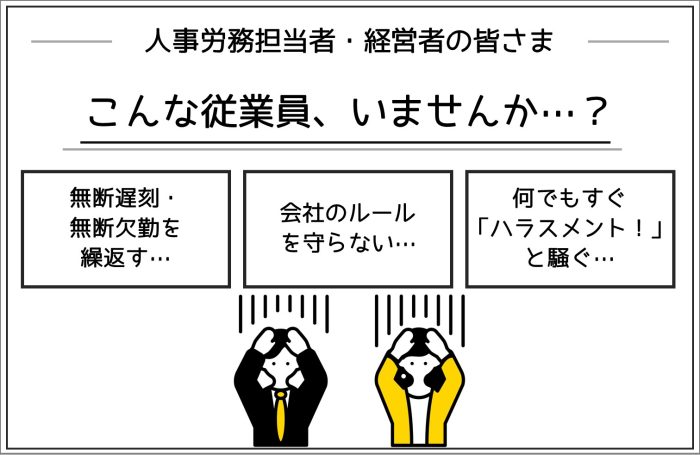【質問】連絡が取れない元従業員への少額賃金の支払い方法
ある従業員が入社初日に短時間の勤務を行ったのち、入社の翌日に退職の意思を電話で申し出てきました。その後、退職手続きのための来社を予定していた日には姿を見せず、以降は電話にも出ず連絡がつかない状態が続いています。
後日、会社から退職届や賃金の振込先に関する同意書等を郵送しましたが、返送もありません。一方で、会社から貸与していた備品(社員証やロッカーの鍵など)は宅配便にて返却されています。
このような状況下で、入社初日に勤務した分の賃金を支払いたいのですが、振込先情報が確認できないため振込による支払いができない状況です。
そこで、このような場合に賃金を現金書留で送付する対応は問題ないか、他に適切な対応方法があれば教えてください。
【回答】現金書留は可能だが、注意が必要
現金書留での支払いは制度上は可能
労働基準法では、賃金は通貨で、かつ労働者本人に直接支払うことが原則とされています。
そのため、本人への直接送付とみなせる現金書留による支払いも法的には許容範囲内です。
ただし、現金書留では郵便局による配達記録は残るものの、本人が実際に受け取ったかどうかの証明が完全にはできない点には注意が必要です。後日、本人から「受け取っていない」と主張される可能性も考慮しておく必要があります。
厳密な対応をとるなら「未払金として保留」も選択肢
法的観点から厳密に対応する場合には、次のような対応が考えられます。
- 本人が取りに来るまで、給与を「未払金」として会社で保管する
- 連絡が取れない限り、直接支払いの原則に基づいて支払いを留保する
ただし、今回のケースのように金額が少額で、本人が取りに来る可能性も低いと見られる場合、実務上は管理負担が大きくなりかねません。
少額であれば実務的には現金書留が妥当な対応
今回のように数千円から1万円程度の少額賃金で、かつ受け取りの可能性が低い場合には、実務的には現金書留での送付が現実的な選択となります。
また、送付記録や送付内容を明記した社内メモ、封筒控え、同封した書類のコピーなど、支払った事実を示す記録を残しておくことが重要です。

現金書留の送付には形式的なリスクはあるものの、少額かつ実務的な視点からは有効な手段です。より安全な対応のためには、送付記録の保管と、送付後の社内処理ルールを明確にしておくとよいでしょう。
まとめ
連絡の取れない元従業員への賃金支払いについては、原則として「現金で直接手渡し」が基本となりますが、実務上は現金書留での送付も適切な方法の一つです。
特に少額であり、本人が来社する可能性が低い場合には、記録を残したうえで現金書留を選ぶことが妥当な対応といえるでしょう。
会社としては、「支払った事実」がきちんと証明できるような備えをしたうえで、労務リスクを最小限に抑えた対応を心がけることが大切です。

この記事は、頻出のご相談事例をもとに生成AIで作成しました。
生成AIでは「それらしい」回答は作れますが、”正確”や”現実的”という面で、経営と人事の世界で回答を利用するには物足りなさが残ります。
お客様の経営状況や人間関係を踏まえた上で、伝え方も含め、現実的な着地点をご提案することは、私たちが得意とする領域です。
記事をご覧になり、「弊社ならどうすれば良い?」と感じられた経営者様・人事担当者様は、ぜひ、私たちにご相談ください。