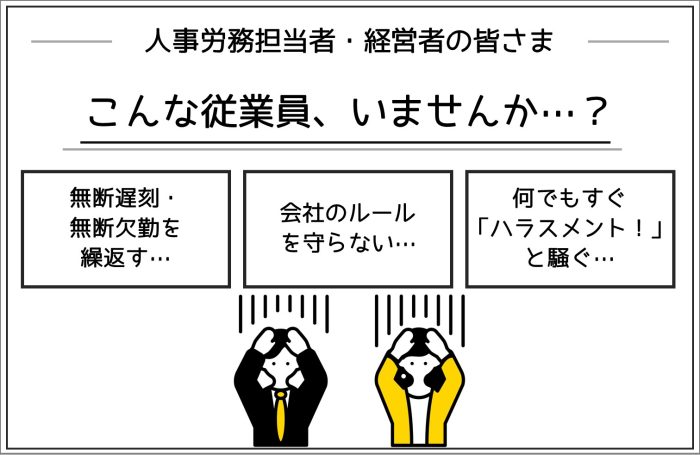奨学金返済に悩む若手社員を支援する制度は、優秀な人材の採用・定着に有効な施策です。特に「入社後3年間働いたら300万円を奨学金返済として支給する」といった制度は、企業の魅力アップにもつながります。
ただし、制度設計を誤ると労働法上のリスクや税務面でのトラブルに発展することもあります。この記事では、制度実施にあたっての注意点や実務的な工夫について、実際の相談事例をもとに整理します。
【質問】入社3年後に奨学金を300万円支給する制度の留意点は?
社員が入社して3年間勤務した場合、300万円の奨学金を会社が肩代わりする制度を検討しています。この制度をうまく運営する上で気を付けるべき点、また、支給される金額が全額給与所得として扱われることについて、効果的な対策やアドバイスがあれば教えてください。
【回答】勤務後の支給ならOK。契約・税の観点で要注意点あり
このような奨学金返済支援制度は、若年層の採用活動において強力な訴求ポイントになります。
一方で、労働基準法や税法の観点から慎重な制度設計が必要です。以下でポイントごとに解説します。
✅支給時期は「勤務後」が原則
前払いにすると「前借金の禁止」に該当する可能性あり
このような制度を導入する際、支給タイミングは「勤務後」であることが重要です。
3年間の勤務を満了した後に支給する制度にすることがポイントです。
一方、入社時に支給し、のちに3年勤務を求める形式は、「前借金の禁止」規定に該当するおそれがあります。

早期退職などのトラブル回避のためにも、「在籍満了後に支給」という形にしておくのが無難です。
✅支給義務は契約時に発生する
原資の確保と契約文面の整備が必須
労働条件の一部として書面に明記することになるため、支給が義務化されます。
よって、将来的に業績悪化などで支給が困難になっても免れることはできません。
また、支給条件として以下のような要件を明文化しておくと、柔軟な対応が可能です。
- 3年間の勤務に欠勤・休職期間が含まれる場合の取り扱い
- 懲戒処分を受けた場合の不支給条項
- 給与とは別枠での支給かどうかの記載

制度導入時は、「あいまいな合意」ではなく、契約書や規定での明確化が非常に重要です。
✅公平性と不満への対策も必要
「奨学金がある人だけ得をする」構造に注意
支援制度は一部の社員にのみメリットがある場合、社内の不公平感を招く恐れがあります。
たとえば、奨学金を返済していない高パフォーマー社員からすれば、「能力に関係なく奨学金があるだけで年収が増える」という不満が生まれることも。
このような懸念に対しては、制度の目的と背景を社内で丁寧に説明する必要があります。

採用強化の施策と位置づけ、現職社員への配慮や別途のインセンティブ制度とバランスを取る工夫が求められます。
✅税務面では「給与課税」扱いに注意
税負担軽減には分割支給などの工夫も有効
支給する奨学金肩代わりの300万円は、原則として賞与扱いとなり、所得税・住民税の対象になります。
その結果、翌年度の住民税が大幅に上昇する可能性もあるため、注意が必要です。
支給方法としては以下のような工夫が考えられます:
- 3年間に分けて100万円ずつ支給する
- 目的を明示して課税扱いをあらかじめ説明する
- 税理士と連携して最適な支給形態を設計する

高額の賞与扱いになる場合、本人の負担増に注意。事前説明と分割支給でカバーするのが実務的です。
支援制度は人材確保に有効、制度設計が成功のカギ
入社3年後に300万円を奨学金返済として支給する制度は、若手人材への強力なアピールになります。
一方で、支給タイミングや契約文面、税務対応を誤ると法的トラブルや不公平感の火種にもなりかねません。
制度設計のポイントをまとめると以下の通りです。
- 「勤務満了後」の支給とする
- 契約・規定での明文化と条件設定
- 社内の不公平感に配慮した説明
- 税負担軽減のための分割支給も検討
社内の雰囲気を壊さず、若手人材の定着を図るうえでも、制度導入前の事前準備と設計が成功の鍵です。
ご不安な点がある場合は、制度設計・規定作成のプロフェッショナルにご相談ください。

この記事は、頻出のご相談事例をもとに生成AIで作成しました。
生成AIでは「それらしい」回答は作れますが、”正確”や”現実的”という面で、経営と人事の世界で回答を利用するには物足りなさが残ります。
お客様の経営状況や人間関係を踏まえた上で、伝え方も含め、現実的な着地点をご提案することは、私たちが得意とする領域です。
記事をご覧になり、「弊社ならどうすれば良い?」と感じられた経営者様・人事担当者様は、ぜひ、私たちにご相談ください。