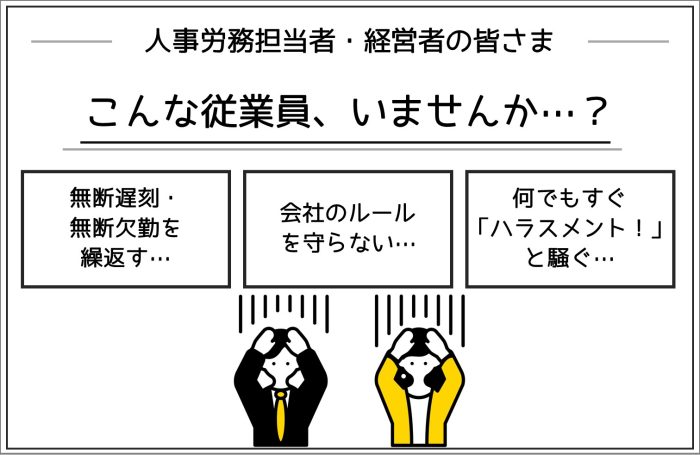【質問】従業員がセクハラ行為を行った場合、企業はどのように対応すべきか
従業員がセクハラ行為で問題を起こしました。当該社員を自宅待機処分とし、社内で懲罰委員会を設置して当該社員の処分を行う予定ですが、自宅待機期間や加害者としての取り扱いはどの程度が適切でしょうか。また、懲罰委員会の開催が遅れる場合、自宅待機を解除することは可能でしょうか?
【回答】自宅待機期間の取り扱いと従業員の処分について
自宅待機の期間に関しては、法的に特定の制限がないものの、常識的には1ヶ月程度が適切とされています。自宅待機は会社都合の休業であるため、休業手当が必要です。また、加害者としての取り扱いについては、刑事事件ではないため社内規定に基づく懲戒処分が行われます。処分は弁明の機会を提供することで公正に進められるべきであり、一般的な処分事例としては、セクハラの内容や悪質性に応じて退職勧奨や諭旨解雇が考慮される場合があります。
懲罰委員会の開催が遅れることによる自宅待機の解除については、自宅待機はいつでも解除可能ですが、懲戒処分としての出勤停止は懲罰委員会の決定後に適用されるため、事前に適用することはできません。会社としての労働力提供の拒否と懲罰の区別を明確にし、正式な処分が下るまでの間、適切な手続きを踏むことが重要です。

この記事ではセクハラ問題に対する企業の対応を解説しましたが、具体的な法的対策や他企業の事例についてさらに詳しい情報が必要な方はお問い合わせください。労働法の専門家として、あなたの企業が直面する困難な状況に対して、専門的なアドバイスと実践的なソリューションを提供します。

この記事は、頻出のご相談事例をもとに生成AIで記事を作成しました。
生成AIでは「それらしい」回答は作れますが、”正確”や”現実的”という面で、経営と人事の世界で回答を利用するには物足りなさが残ります。
お客様の経営状況や人間関係を踏まえた上で、伝え方も含め、現実的な着地点をご提案することは、私たちが得意とする領域です。
記事をご覧になり、「弊社ならどうすれば良い?」と感じられた経営者様・人事担当者様は、ぜひ、私たちにご相談ください。