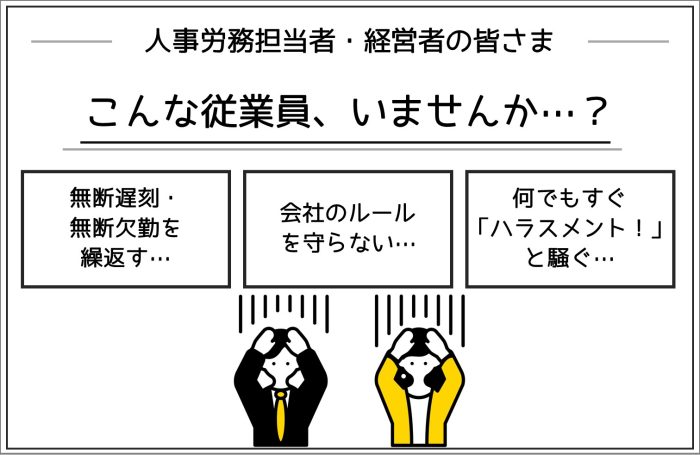【質問】振替休日の取得期限を過ぎた場合の法的扱いは?
当社では休日出勤に対して、あらかじめ代休制度ではなく振替休日制度を設けており、「振替日は指定せず、3ヶ月以内に取得する」というルールで運用しています。
しかし実際には、忙しさから3ヶ月以内に振替休日を取得できずに消滅してしまうケースもあります。
このような場合、
- その振替休日は「放棄」された扱いになるのでしょうか?
- あるいは「代休扱い」となり、割増賃金の支払いが必要になるのでしょうか?
法律上の対応についてご教示ください。
【回答】振替休日が取れなければ割増賃金の支払いが必要
振替休日は期限を過ぎると未払い賃金の問題に
ご質問の件ですが、振替休日の扱いに関して法律で明確な取得期限の定めはありません。ただし、行政通達では「できる限り振替日から近接した日であることが望ましい」とされています。
(昭37.7.5 基発968号、昭63.3.14 基発150号)
とはいえ、給与計算期間をまたいで未取得となった場合には、労務管理上・賃金支払い上の問題が生じます。
振替休日が取得されなければ、当該休日の労働に対する割増賃金の支払い義務が発生します。そのため、遅くとも同じ給与計算期間中に消化・処理する必要があります。
割増率は休日の種類によって異なる
休日労働に対する割増率は、どの休日に出勤したかで異なります。
たとえば、土日休みの企業の場合、
- 法定休日(週1回の最低休日)に勤務した場合:1.35倍の割増賃金
- 所定休日(土曜など)に勤務した場合:1.25倍の割増賃金
となります。どちらに該当するかは、休日の位置付けを明確にしておくことが重要です。
時間外労働との関係にも注意が必要
振替休日が消化されないまま休日出勤がカウントされると、月間の時間外労働時間にも影響します。
特に大企業では月60時間を超える時間外労働については、割増率が1.5倍になるため、管理を怠ると労務リスクが高まります。
また、休日を振り替えたことによって1週間の労働時間が法定労働時間(原則40時間)を超える場合は、その分が時間外労働となり、36協定の対象となります。(昭和23.11.27 基発401号)
実務的な対応と就業規則の整備が鍵
振替休日が適切に取得されないケースに備え、就業規則等に以下の点を明記しておくことが望ましいです。
- 振替休日の取得期限と未取得時の扱い
- 割増賃金を支払う旨のルール
- 給与計算期間内に清算する方針
これらを整備しておくことで、社員とのトラブル防止にもつながります。

振替休日は「取れなければ終わり」ではなく、取れなかった場合の処理も明確にしておくことが会社運営上大切です。割増賃金の支払いを怠ると、未払い賃金問題に発展しかねないため、早期の管理と対応が重要です。
振替休日が取得されなかった場合は、その休日出勤に対して割増賃金を支払う必要があります。
就業規則には取得期限だけでなく、取得できなかった際の対応方針も明記し、給与計算期間内での管理を徹底しましょう。
振替休日の扱いは、放置せず、就業管理と労働時間管理の両面から整備しておくことが、トラブル防止の鍵になります。

この記事は、頻出のご相談事例をもとに生成AIで作成しました。
生成AIでは「それらしい」回答は作れますが、”正確”や”現実的”という面で、経営と人事の世界で回答を利用するには物足りなさが残ります。
お客様の経営状況や人間関係を踏まえた上で、伝え方も含め、現実的な着地点をご提案することは、私たちが得意とする領域です。
記事をご覧になり、「弊社ならどうすれば良い?」と感じられた経営者様・人事担当者様は、ぜひ、私たちにご相談ください。