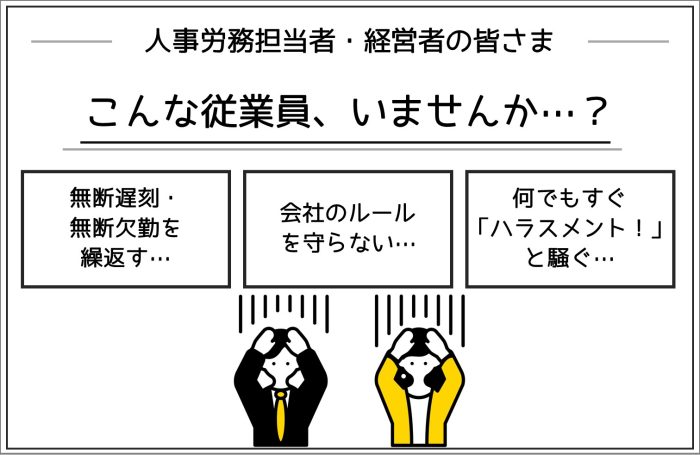【質問】資格取得費用の返還を退職時に求める運用は妥当か?
当社では、業務上必要な資格(たとえばサービス継続や加算に必須なもの)について、取得費用や更新費用を会社が負担しています。ただし、3年以内に退職した場合には、当該費用の返還を求める旨の書類を取り交わしています。このような運用は、法的に問題ないのでしょうか。
【回答】業務上必要な資格であれば「返還請求」は法的に困難
業務に直結する資格の場合は返還請求が難しい
労働基準法第16条では「損害賠償の予定」を原則禁止しています。
そのため、業務に必要な資格取得費用を労働者に後から請求することは、事実上「退職制限」や「制裁」と見なされる可能性があります。
よって、原則としては「ナシ」と考えた方が安全です。

あくまで「業務命令で必要となる資格」は、会社が自らの都合で社員に取らせるものなので、費用負担も会社が原則です。
業務と直接関係がない資格なら返還請求の余地あり
業務との関係が薄い、または任意取得の資格であれば、「返還特約」が有効とされる余地はあります。
ただし、対象資格の明確化や事前合意、金額の妥当性などが問われるため、一律に「3年以内は返還」ルールを適用するのはリスクがあります。

高額な海外留学やMBA取得に関する裁判例でも、「労働契約の自由」が制限される方向で判断されています。
実務的には「返還条件」よりも「支給対象の見直し」を
仮にタダ乗りを防ぎたいのであれば、「費用返還」ではなく、「取得支援の対象者を勤続3年以上の者に限定する」といった運用が現実的です。
これにより、法的リスクを回避しつつ、長期勤務を促す効果も見込めます。

実際には、返還請求を訴訟で争っても、費用対効果は見合わないことが多い点にも注意が必要です。
運用上のアドバイス:制度設計と説明を丁寧に
費用返還の取り決めについては、社員への説明や書類の整備だけでなく、目的・対象資格・対象者・期間・返還額などの要件を明確にすることが大切です。
不明確なままでは、制度自体が無効とされるおそれがあります。

書類だけでなく、「制度そのものの設計思想」が重要です。経営理念や人材育成方針との整合性も求められるでしょう。
資格取得費用の退職時返還の取り扱いは、資格の業務性や契約内容によって法的評価が分かれます。
業務に必要な資格であれば返還は難しいですが、任意性が高ければ一部認められることもあります。とはいえ、実務的には「返還の仕組み」よりも「支給対象者の選定」で対応する方が望ましいといえるでしょう。
制度設計の際には、労務トラブルの予防と社員との信頼関係のバランスに留意することが重要です。

この記事は、頻出のご相談事例をもとに生成AIで作成しました。
生成AIでは「それらしい」回答は作れますが、”正確”や”現実的”という面で、経営と人事の世界で回答を利用するには物足りなさが残ります。
お客様の経営状況や人間関係を踏まえた上で、伝え方も含め、現実的な着地点をご提案することは、私たちが得意とする領域です。
記事をご覧になり、「弊社ならどうすれば良い?」と感じられた経営者様・人事担当者様は、ぜひ、私たちにご相談ください。