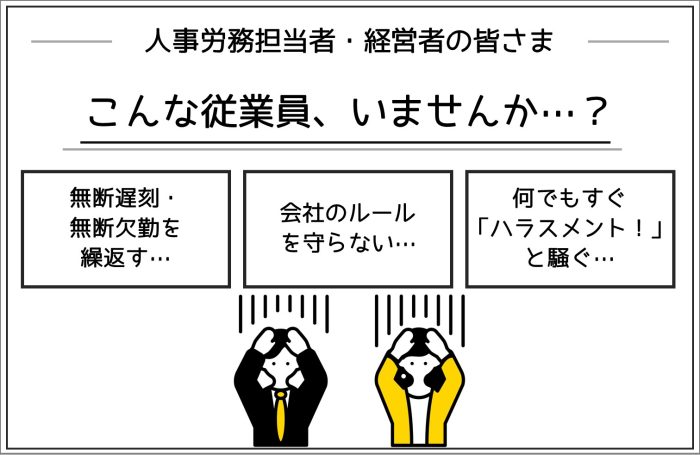【質問】祝日に勤務した従業員から手当請求。支払いは必要?
飲食店で雇用している従業員を祝日である4月29日に勤務させ、5月1日は休業としました。その後、GW中の他の祝日はすべて休みにしていますが、従業員から「4月29日は本来休みなのに出勤したのだから、手当を支払ってほしい」と言われました。支払うべきかどうか判断に迷っています。加えて、休日や祝日の考え方についても改めて知りたいです。また、今後の契約内容についてのアドバイスもお願いします。
【回答】振替休日を事前に指定していれば手当は不要。契約内容の明確化を
祝日の勤務が休日出勤になるとは限らない
休日は会社が定める日であり、カレンダーの祝日とは無関係です。
4月29日の勤務に関しては、事前に5月1日を振替休日として指定している場合、4月29日は通常の勤務日とみなされます。このため、法定の休日出勤や割増賃金の対象とはなりません。

振替休日の指定は事前に明確に行い、労働者に説明しておくことがトラブル防止に繋がります。
割増賃金の基本ルールを理解する
時間外や休日労働の割増賃金は法定条件を満たした場合のみ発生します。
労働基準法上、1日8時間・週40時間を超える労働には25%の時間外割増が必要です。また、週に1日も休みがない=7連勤以上の場合は35%の休日割増が必要です。今回のケースでは、振替休日を取得しており、これらの条件に当てはまらないため、割増賃金の支払い義務は生じません。

法定条件に基づく支払い義務と、労働者の誤解を正す説明のバランスが求められます。
契約内容を見直し、明文化する
労働時間・休日・インセンティブなどの条件を契約書に明記しましょう。
これまでの運用を踏まえ、以下の点を契約書に盛り込むことをおすすめします。
- 始業・終業時刻を明記し、遅刻・早退時の取り扱いを定める
- 休日は店舗カレンダーによって決定することを明記
- 振替休日や達成金制度の運用ルールを具体化
特に達成金については、売上目標ではなく営業利益ベースに切り替えることで、現実的な運用が可能になります。

契約条件を曖昧なままにしておくと、期待値のズレが蓄積し、労使間の信頼関係を損なう恐れがあります。
祝日の勤務がすべて割増賃金の対象になるわけではなく、会社の定める休日との関係が判断基準となります。今回のように、振替休日を事前に設定している場合は、法定の割増賃金支払い義務はありません。今後は、契約書や運用ルールを明文化し、誤解や不満が生じない体制づくりが重要です。労働者への説明責任と経営者としての判断を両立させることが、円滑な店舗運営に繋がります。

この記事は、頻出のご相談事例をもとに生成AIで作成しました。
生成AIでは「それらしい」回答は作れますが、”正確”や”現実的”という面で、経営と人事の世界で回答を利用するには物足りなさが残ります。
お客様の経営状況や人間関係を踏まえた上で、伝え方も含め、現実的な着地点をご提案することは、私たちが得意とする領域です。
記事をご覧になり、「弊社ならどうすれば良い?」と感じられた経営者様・人事担当者様は、ぜひ、私たちにご相談ください。